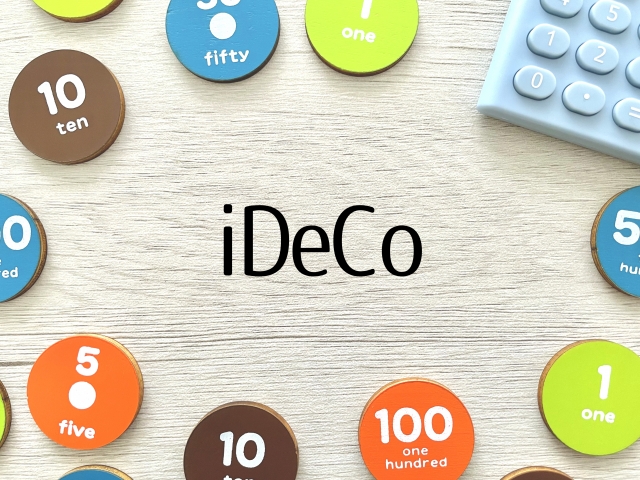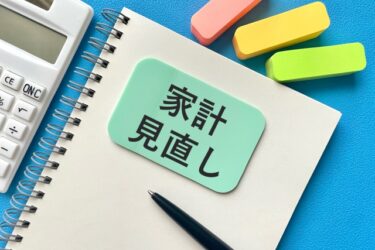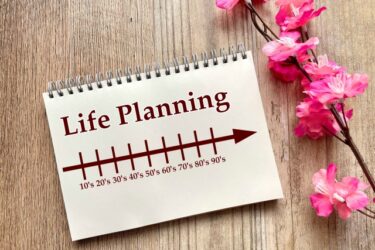iDeCo(イデコ)は、日本で提供される個人型確定拠出年金制度のことです。
この制度は、自分自身で掛金を拠出し、その掛金を運用して将来の年金を準備する仕組みです。
2001年にスタートし、2017年以降は加入対象者が大幅に拡大されたため、多くの人が利用できるようになりました。
主な目的は、公的年金(国民年金や厚生年金)を補完し、老後の生活資金を充実させることです。
加入者は自分で投資商品を選び、運用成果によって受け取る金額が変わるため、自身の将来の資産形成に対する責任と自由度が高いのが特徴です。
iDeCoの仕組み
掛金の拠出
加入者が毎月一定額の掛金を拠出します。掛金の上限額は職業によって異なり、以下のように設定されています。
- 自営業者(国民年金第1号被保険者): 月額68,000円(年間816,000円)
- 会社員(厚生年金に加入している第2号被保険者): 月額12,000円から23,000円(企業型DCがない場合)
- 公務員や教職員: 月額12,000円
- 専業主婦(主夫)(国民年金第3号被保険者): 月額23,000円
運用商品を選ぶ
掛金は、金融機関が提供する以下のような運用商品に投資されます。
- 投資信託
- 定期預金
- 保険商品
- 国債や地方債
運用成績に応じて、将来受け取れる金額が増減します。
運用リスクを抑えたい場合は、定期預金や保険商品を選ぶことも可能です。
受取時期と形式
原則として60歳以降に受け取ることができます。
受取方法は次の3種類から選べます。
- 一時金として一括受取
- 年金形式で分割受取
- 一時金と年金形式の併用
受取時には税制優遇が適用され、退職所得控除や公的年金等控除を受けられます。
iDeCoのメリット
掛金が全額所得控除の対象
iDeCoの最大のメリットは、拠出した掛金が全額所得控除の対象となることです。
これにより、課税所得が減少し、所得税と住民税が軽減されます。
例)年間240,000円を拠出した場合:
- 所得税率10%の場合、年間24,000円の節税効果
- 住民税10%の場合、年間24,000円の節税効果
合計で年間48,000円の税負担が軽減されます。
運用益が非課税
通常、金融商品の運用益には約20%の税金がかかりますが、iDeCoでは運用益が非課税となります。
これにより、運用効率が大幅に向上します。
受取時の税制優遇
iDeCoで積み立てた資産を受け取る際にも税制優遇が適用されます。
- 一時金として受け取る場合:退職所得控除が適用
- 年金形式で受け取る場合:公的年金等控除が適用
iDeCoのデメリット
60歳まで資産の引き出しができない
iDeCoは老後の資産形成を目的としているため、原則として60歳になるまで掛金や運用益を引き出すことができません。
これが最大のデメリットとされることが多いです。
手数料がかかる
iDeCoには運用中に以下のような手数料が発生します。
- 加入時の初期費用
- 運用管理手数料(毎月)
- 資産を移管する場合の手数料
金融機関によって手数料の金額が異なるため、加入前に比較検討が必要です。
運用リスクがある
投資信託などリスクの高い商品を選んだ場合、元本割れの可能性があります。
運用商品の選択は慎重に行う必要があります。
iDeCoの始め方
- 金融機関を選ぶ
iDeCoを取り扱っている金融機関(銀行、証券会社など)を選びます。
各金融機関が提供する運用商品や手数料を比較し、自分に合ったものを選びましょう。
- 加入申し込み
選んだ金融機関で申し込み手続きを行います。
必要な書類は以下の通りです。
- iDeCo加入申込書
- マイナンバーカードのコピー
- 国民年金保険料の納付状況を確認できる書類(自営業者の場合)
- 運用商品を選択
加入後、運用商品を選びます。
初めての場合は、リスクを分散させるために複数の商品に投資するのがおすすめです。
- 掛金の拠出を開始
申し込みが完了すると、毎月の掛金が口座から引き落とされ、運用が開始されます。
iDeCoを利用する際の注意点
- 資産運用のリスクを理解する
iDeCoは運用成果に応じて将来の受取額が変動します。
元本保証の商品を選ばない限り、リスクを伴うため注意が必要です。
- 手数料に注意する
金融機関によって手数料が異なるため、運用コストが低いところを選ぶことが重要です。
- 長期運用を前提とする
iDeCoは短期的な利益を目指すものではなく、老後資産を計画的に形成するための制度です。
長期的な視点で運用する心構えが必要です。
iDeCoの活用例
ケース1:節税効果を最大限活用
会社員のAさん(年収500万円、所得税率20%)がiDeCoに月額23,000円を拠出する場合、年間の節税額は以下の通りです。
- 所得税の節税額:23,000円 × 12ヶ月 × 20% = 55,200円
- 住民税の節税額:23,000円 × 12ヶ月 × 10% = 27,600円
合計で年間82,800円の節税効果があります。
ケース2:運用益非課税の恩恵
Bさんが毎月10,000円を30年間積み立て、年利3%で運用した場合、運用益は約250万円に達します。
この運用益に対する税金(約50万円)が非課税となるため、大きなメリットがあります。
まとめ
iDeCoは老後の資産形成を効率的に行える制度であり、特に税制優遇が大きな魅力です。
ただし、60歳まで資金を引き出せないことや運用リスクがある点には注意が必要です。
ファイナンシャルプランナーに無料相談するのも節約の近道です。リクルートが運営する保険チャンネル
自身のライフプランに合った運用を行い、制度を最大限活用しましょう。